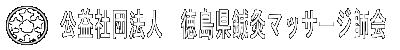 |
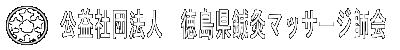 |
|
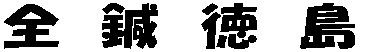 第24号 平成22年2月24日発行 全鍼大会報告 第8回全鍼師大会参加レポート 泉木 礼子 全国大会に参加するのは愛媛県で開催以来、2度目の参加で日東医は初めての参加でした。11月初め寒波と共に札幌入りしホテルと外気の差は20度以上、初雪も舞って北の大地で充実した時間を過ごしてきました。 初日は開会式の後、全員参加の1.特別講演「住民と共に守る健康」があり、続いて学術局の分科会2.3.に参加しました。その後、4.学術講演「響き合う医療とは」があり、夜は懇親会で親睦を深めました。 1.特別講演「住民と共に守る健康」 講師は村上智彦先生、夕張市の破綻を背景に40億円もの負債を抱え経営難に陥った市民病院の医師で、現在は夕張医療センター長、医療法人「夕張希望の杜」理事長として地域医療に取り組んでいます。 19床の診療所、40床の老健施設、在宅90軒を受け持ち、地域を支える医療を実践している様子が紹介されました。平均寿命が長く医療費が少ない長野県は検診率が高く北海道は逆に検診率が低く、医療費が高くなっています。夕張の地域再生の一つとして、住民の健康意識を高めて検診率を上げ医療費を抑えることが重要です。  独居高齢者に対する緊急の備えとして「命のバトン」と呼ばれるものが考案されました。連絡先、病名、かかりつけ医など個人情報を書いたものを円筒状のケースに入れて冷蔵庫に入れておくように統一しておけば迅速な対応がとれます。地域医療では包括的に予防的な取り組みをしていくことが重要です。 病気と闘う医療が先進医療、専門医療だとすれば、地域医療は支える医療、消えていく人々の死に場所作りの一面もあります。予定の時間をオーバーしての講演にマイナスからのスタートとなった再生にかける強い思いを感じました。今回の講演では膨大な負債を改善するには個々の健康意識が何より大切で自分の健康は自分で守るという健康意識が医療費をおさえることになり自治体の財政安定にもつながるということを強調されていました。 2.鍼灸医療推進研究会シンポジウム 鍼灸医療推進研究会は関係4団体(東洋療法学校協会、全日本鍼灸学会、日本鍼灸師会、全日本鍼灸マッサージ師会)で組織されたもので、より質の高い鍼灸医療の提供と鍼灸需要喚起を目的として5ヶ年計画で活動をしているものです。 研修、研究、普及啓発の3つの作業部会の各会長より3ヶ年中間報告と今後の活動について発表の後、フロアと質疑応答が行われました。 ≪研修作業部会 小川卓良部会長≫ (活動)後輩を育て全体を高めるため卒後研修を開業鍼灸師の手で行うように卒後研修科目の設定、卒後研修評価表の作成、臨床実習機関基準の作成を行なった。また、卒後研修テキスト作成委員会を設置して保険適応疾患+膝痛の鑑別基準のテキスト・スライド作成などを行った。 (今後)東洋療法研修試験財団、東洋療法学校協会と卒前、卒後、生涯研修の内容の整合性を図る。卒後研修講習会の内容を具体的に作成する。 (パワーポイントとテキスト) 卒後研修制度を試験的に行う。 健康保険指定鍼灸師及び広告制限について省庁、損保協会と折衝する。 ≪研究作業部会 川喜多健司部会長≫ (活動)変形性膝関節症に対する鍼の効果のエビデンスを集め、その成果を普及することを目的に活動してきた。 ・膝OAに対する鍼の効果をテーマにした ・国際シンポジウムで成果を発表した。 ・日韓の膝OAに対する実態把握を行った。 ・患者の受診行動に対するアンケートを鍼灸院と整形外科医院で実施した。 ・鍼の臨床研究では頸部症候群や慢性閉塞性肺疾患に一定の効果を確認した。 ・同一被験者に日中韓で伝統的診断と治療を行い脳の活性化と白血球成分を指標に効果の検討を行った。 (今後)整形外科を含む医療機関で膝OA患者に対する臨床実験の実施。膝OAに対する鍼灸治療のベストケースの集積とそのデータベース化 ≪普及啓発作業部会 杉山誠一部会長≫ (活動)2006年より大手広告代理店と委託契約を結び、鍼灸についてメディアを活用した広報活動を展開してきた。2007年9月報道基礎資料を作成し、関係4団体と報道関係各社に送付した。同12月にはニュースレターno.1を発刊、メディア各社に400部送付し今年4月にはno.4「五月病と鍼灸」を送付した。2008年12月「鍼灸net(http://www.shinkyu-net.jp)」を開設一般やメディアに向け、さらに分かりやすい情報発信を検討中である。(今後)今後も鍼灸netやニュースレターによる情報提供に努め、露出機会の増大につなげていきたい。 3.マッサージ等将来研究会報告 この研究会は平成20年6月、業界6団体(全鍼・日マ・日盲連・全病理・理教連・学校協会・日東医)で構成され、代表には本会の杉田久雄会長が選ばれ、3つの部会(法令部会、生涯・教育部会、普及・啓発部会)で活動しています。それぞれの部会の活動に参加している全鍼師会副会長3氏により報告がありました。 ≪法令部会 川村雅章法制局長≫ ・無資格者対策を中心に活動している。 ・他の医療関係の法令(医師法、歯科医師法、薬剤師法、理学療法士法、保健師助産師看護師法など)と比べると目次がない、目的がない、届けが空白であるなど課題があり検討を重ねている。 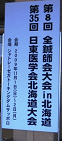 ≪生涯・教育部会 高田外司学術局長≫ ・生涯研修のあり方と有資格者の認定制度 ・生涯研修の他団体との相互乗り入れ ・財団主催の研修実施の勧め方 ≪普及・啓発部会 山本登総務局長≫ ・鍼灸医療推進活動とのすり合わせ ・リンパドレナージはあ・マ・指の業務域であり、研修を実施して学会認定(日東医)の方向を検討中学術局の分科会に参加して鍼灸、マッサージともに法的な安定、基礎的な研究で科学的な裏付け、卒前、卒後、生涯研修などでレベルアップ、メディアや一般への普及と各部が連携して向上していくことで力強い動きが生まれるように感じました。 4.学術講演「響き合う医療とは」 講師は「響きの杜クリニック院長」西谷雅史先生医学博士 産婦人科学認定医 48歳 更年期障害の治療に関わるなかで「気」の世界に興味を持ち太極拳や呼吸法の実践から「気」の存在を確信し自然治癒力に働きかける代替医療に関心をもつようになりました。病気は様々な内的、外的ストレスによる心身の不調和から起こるので治療は環境、心と体、周囲の人との調和を保つことが基本となり、これらの「調和」が医療の基本と考えます。これを「響き合う医療」と名づけ3年前にクリニックを開設し、症状は現代医学的な対症療法で緩和させる一方、代替医療で自然治癒力を引き出し病気にならない心身づくりを実践しています。おもな代替医療は漢方薬、呼吸法、気功、断食、カウンセリング、バッチフラワー、ホメオパシー、心理療法などを行っています。現代は心身の不調に様々なストレスや電磁波など環境が大きく影響しているようです。 2日は日東医学会の統合医療とコメディカルについてのシンポジウムに参加しました。はじめに4氏より、症例、難病の診断、リハビリなどの発表がありました。 ・膠原病など鑑別する為の視診・関節可動域・触診について(あかしあ労働福祉センター 麻生道弘) ・臨床実習におけるパーキンソン病患者の一症例(北海道高等盲学校教諭 岡部博之) ・パーキンソン病、関節リウマチなどのリハビリテーション(北大大学院保健科学准教授 高橋光彦) ・ALS及びパーキンソン病の鍼マッサージ症例(中央鍼マッサージ治療室 藤本定則) 統合医療を行っていく際、それぞれの職種が独自の専門性を生かしながら全体としてのチーム医療作りが重要だと思いました。 全鍼大会、日東医学会の合同開催で、分科会や発表など4会場で同時進行しており介護予防や接遇などの分科会にも興味をおぼえました。業界が取り組んでいることを実質1日間で展開するには中央の準備も大変なものであったろうと思いました。 大会終了後は、参加者12名で北海道の雄大な自然と北のグルメを十分に堪能し2泊3日の研修旅行を無事終わりました。  第8回「全鍼師会大会in北海道」に参加して 濱崎 倫宏 11月1日、2日、「第8回 全鍼師会大会in北海道」に参加しました。今回は徳島から総勢12人、西日本からの参加としては抜群の参加人数で本県師会の意気込みの高さがうかがえます。 今回の会場は、広大な土地にそびえる堂々としたたたずまい、エステ・チャペル・天然温泉完備、ウォータースライダー付屋外プール、冬でも安心屋内温水プール、至れり尽くせりのホテルリゾート「シャトレーゼガトーキングダム サッポロ」です。 特別講演は夕張市で医療法人の理事長をされている医師、村上智彦氏による「住民と共に守る健康」というテーマで1時間以上ギッシリ話をして頂いた。徳島県は他人事ではない!自治体の財政状況はひっ迫、糖尿病を始めとする県民の健康に対する意識も低い。夕張を他山の石と出来るか否かで、5年後、10年後の徳島の未来は変わる。と思わせる講演だった。必要なのは現状を打破する意識改革だ。 特別講演が延びたので分科会が遅れてしまい大忙し。慌てて会場移動、次は保険局分科会「保険取扱いディスカッション」に参加する。今回は3時から保険取扱の現状報告と議題提案、休憩を挟み4時から会場を右側(保守派、穏健派)左側(改革派、急進派)に分けて出席者同士で議題を討論する、という趣向。僕は、出入り口に近いから左側へ座った。議題として 1.同意書をなくす(不必要にする)には? 2.保険者との団体協定を実現するには? 3.業界団体はこれから何をすべきか? 等で討論するはずが、政権交代の折もあり、話が予定とはあらぬ方へ進み、日医会との関係や会の支持政党の変更へと話は流れる。 共通認識として現在の状況の不透明感があるのだが、イマイチ話が噛み合わないままタイムアップで終了・・・消化不良だった。 僕は、民主党はEPA、FTA推進派なのだから、本当に国会議員に「鍼灸マッサージを考えてもらう」なら「超党派」ではなく、民主の先生にこそ、しっかり考えてもらいたいと思うのだが、それはこれまで築いてきた自民党との橋頭堡を崩す事になるのだろうか? 吉井局長を始め同意書撤廃の為、努力を続けてこられ方々には頭が下がる。全く先が読めない時代になってしまった。 次の分科会は「全国のスポーツセラピー徹底比較!」まずは新潟県から、国体をきっかけにマッサージ協会を設立し大会終了後も組織を継続、3年後のインターハイに向けて準備中との報告。 次に栃木県からは県内5団体合同で毎月1回、1年間12回の有料セミナーを実施、認定試験を行い5年毎更新にしたが、認定者数が100名→60名に減少、お金を『払って』ボランティアがどうも、なじまなくなってきた』との報告 熊本県からは3団体1本化の報告、次は公益法人化を目指すそうだ。こちらも国体をきっかけに3年間10万円でセミナー実施、現在受講者100名で国体後も活動を継続している。各地の報告の後、全鍼師会学術委員の中田先生のスライド「スポーツ鍼灸マッサージと消毒法」室内施設や屋外施設でボランティア治療を行う際の注意点や設置例など細かい説明をして頂く。今後の徳島県の活動でも役立ちそうだ。 最後に質問で「だんだんボランティア参加人数が減っていく・・・」これは、どこの都道府県でもある普遍的な問題のようだ。やはり答えも「細く・長く、が基本で『新人の勉強の場所』にして先輩の治療者の長所、技術を盗む場所にする」だった。 時間が押してバタバタとした分科会だったが次は気楽な学術講演「響き合う医療とは」札幌市内で統合医療を行うクリニックを開院しておられる医学博士、西谷雅史先生のお話を聞く。 現代医療に漢方、呼吸法、気功、断食、等を取り入れ自己治癒力を高めて、病気になりにくい身体を作る事に重点を置く治療方針はまさに「未病治」!こんな先生が増えると同意書、診断書に苦労しないのだが・・ 懇親会は、まずサッポロビールで乾杯!ビールもいいのだが、なにより目当ては北海道の味覚!余興でよさこいソーラン踊りが始まります。阿波踊りのような決り事が無く、曲や構成、振り付けが自由でダイナミックです。テレビでは何度か観た事あるのですが目の前で見ると迫力が違います。クライマックスはいくつもの和太鼓のリズムに合わせて全員で激しく踊ります。思わず食事の手が止まり魅入ってしまいました。続いて、打って変わって静かな三味線と唄と舞が始まりました。男性の弾く三味の音色に女性の唄声、どことなく寂しい響きのある民謡、漁歌、江差追分に拍手が鳴り止みません。飽きの来ない出し物が続き、料理も最高で言うことなしです! これまで行った全鍼師会大会の中で一番楽しかった懇親会でした。 2日目の朝早く起床、すると初雪、現在気温0度、数秒間で鳥肌が立ちます。冬になると関節痛がひどくなる患者さんの顔も頭に浮かびます。 2日目に出席するのは「早わかり介護予防 実編」です。本来、我々鍼灸マッサージ師の得意分野であるはずの「未病治」ですが、現在、徳島で介護予防にそのノウハウを活かせられる余地はありません。しかし一部の自治体では(だいたい経済的に余力のある自治体ですが、既に鍼灸マッサージ師がその力を遺憾なく発揮しています。ここではその現状報告と実際に行われているテクニックとノウハウの研修が行われました。 現段階で介護予防に門戸を開放している自治体はわずかですが少ないながらも実績を収めている治療家、治療院もあります。 神奈川県川崎市では入札を経て1施設、年間280万円で週1回講演会や体操指導を行っています。神奈川県二宮町は社会福祉協議会からの依頼で1回2,600円、15ヶ所の公民館でミニデイサービスを行っています。そのほか、転倒予防教室、筋力トレーニング、等など。 地域によって金額、内容はマチマチなのですが入札等で参加できる自治体が増えてくると徳島県も追随するか?とも思いますが、まず何より「先だつ物」がありません・・・難しい。 休憩を挟んで実技指導に移ります。朝日山先生による長机を二つ並べて即席のベッドを作ってのフロアエクササイズと椅子に座ったままで出来るチェアーエクササイズを行いました。まず経絡を利用したストレッチから入ります。最初は体が硬くてお年寄りでもできる運動ができません・・・。それが経絡ストレッチを少しするだけで、みるみる柔軟性が増していきます。エクササイズもストレッチもどんどん練習して身に付けたいものですが・・・なにしろ活かせる場所がないのが痛いところです。  2日間の分科会日程がすべて終わり、フリートーク「全鍼師会と日東医の将来展望」から閉会式で全鍼師会大会の全日程が終了しました。これからは楽しい観光の始まりです。 バスに乗り込み最初に向かうのは札幌場外市場。観光バス専用の駐車場まであり、もはや札幌の観光名所の1つになっています。道路を挟んで両側にビッシリ商店が立ち並んでいて魚介類、野菜、乾物、加工品、北海道土産のほとんどがここで手に入ります。お土産には不向きですが「札幌大珠」という人頭の3倍はある巨大なキャベツや当たり前のように箱単位で売られるジャガイモ、タマネギ、果物。イケスで動いている巨大タラバガニにマツバガニに毛ガニ。ボタンエビも新鮮で透明な体の中で卵がエメラルドグリーンに輝いています(10センチ程のエビ1匹で800円ですが・・・)ホッケの開きだって徳島では見た事ない大きさでビックリします。 昼食は、「海鮮食堂 北のグルメ亭」という店に入りました。いろんなメニューの中から僕が選んだのは「イクラ丼」。店独自の漬ダレで味付けされたルビー色の小粒のイクラが、ご飯が見えない程どっさり乗せてあって大満足の逸品でした。1粒1粒は普段見るイクラより小さいのですが皮が薄く、プチッと弾力があって、濃厚なのに生臭みが一切無く、これまで食べたどのイクラより美味しかったです。 次の目的地は、大倉山シャンテ。スキーのジャンプ台のある場所です。なにしろ山の中、寒い、寒い!表彰台で記念写真を撮影した後は頂上までリフトで上がります。これがまた寒い・・・頂上に到着するまでは異常に長く感じましたが、シャンテ最上部から見る風景が全てを忘れさせる遠く札幌の街並みが一望できる絶景です。相変わらず雪は降り続いて、雪雲のグレー、冬山のグレー、街のグレー、これらが1枚の水墨画のような見事な色の階調を作り出し、時間が止まったかの様な錯覚を起こします。一時はどうかなるかと思いましたがホントに来て良かった・・・。 温かいバスに戻り、ホット缶コーヒーをすすりながら市街地に戻ります。30分程で現代都市の中に庭園と赤レンガのレトロな建造物、北海道庁の旧庁舎に到着しました。長い時間風雪に耐えてきた赤レンガに歴史を感じます。昔の建物なので階段のピッチや扉の大きさに窮屈さを感じますが、それもまた歴史の重みを感じさせます。建物を一巡して庭園へ歩きます。街のド真ん中にありながら池と大樹に囲まれた、エゾリスや野鳥の囀りの聞こえてきそうな、趣のある庭園ですが、聞こえてくるのは街の喧騒と車の音、そしてカラスの鳴き声。無料開放されていて自由に歩き回れる事をいいことに、庭園の方までグルリと回っていたせいで、皆さんを長い間バスで待たせてしまいました・・・反省。 夕食は、サッポロビール園でジンギスカンの食べ放題+飲み放題楽しい時間でした。2日連続でビールを飲んで、たらふく食べて、大満足。ズボンがキツイ。皆さんはこれから2次会でカラオケですが、僕はまたもや別行動、これが僕の北海道旅行の裏テーマ「今は東京と札幌でしか稼動を確認されていない昔のゲームを15年ぶりに遊ぶぞ!」です。腹ごなしに20分位、迷いながらゆっくり歩いて目的のゲームセンター到着、懐かしいゲームを堪能しました。 最終日は、昭和新山、札幌から高速道路で2時間程の移動。大都会の札幌と打って変わって、のどかな山林と河川、牧草地が続く。今日も雪が降ったりやんだり。高速を降り山道へ、洞爺湖に向かう道を逸れ、道路の傾斜が強くなる。 トンネルを抜けると、荒々しく水蒸気を上げる。昭和新山と無骨な有珠山が徐々に姿を現わしてくる。昭和新山の観光駐車場に到着。駐車場は一面の雪景色、山自体は地熱ですっかり融雪しているせいで余計にコントラストがクッキリ出ている。滑りやすいので気をつけて記念撮影と土産物屋を巡りました。 昼御飯は、「かに御殿」に!山道から一転海岸線を走ります。屋根の上に巨大な熊と鮭と蟹が鎮座している不思議なドライブイン。それが「かに御殿」。ここでカニセイロ御飯カニ味噌汁、の蟹尽くし定食。カニのダシがしっかり効いた味噌汁は、ダシ用のカニのブツ切りをホジホジ食べながらすすると体が温まります。 最後の目的地は「白老ポロトコタン」アイヌの民族文化を継承していく施設で、昔の住居が忠実に再現されていて、風習の解説や伝統の歌と踊りを観る事ができました。あっという間の2泊3日でした。あちらこちら、おもしろい所も回れておいしい物も食べられて、勉強も少しがんばりました。来年の全鍼大会は金沢!今から楽しみです。
|
 |
公益社団法人 徳島県鍼灸マッサージ師会 事務局 〒770-0831徳島県徳島市寺島本町西1丁目60-5 Tel&Fax 088-625-2412 Copyright (C) 2004-2011 Tokushima Acupuncture,Moxibustion and Massage Association. All Rights Reserved. |